建築基準法において、「倉庫」と「倉庫業を営む倉庫」は、その利用目的によって明確に区別され、適用される基準が異なります。主な違いは、他人の物品を保管する事業(倉庫業)を行うかどうかにあり、それによって建築物に求められる安全性や機能に関する要求が大きく変わります。
端的に言えば、「倉庫業を営む倉庫」の方が、より厳しい建築基準や関連法規(倉庫業法)をクリアする必要があります。

南都留合同庁舎 倉庫棟

山梨牛乳運送株式会社 冷蔵庫倉庫
主な違いのポイント
「倉庫(自家用倉庫)」
主な用途 自社の物品や個人の財産を保管
関連法規 建築基準法、消防法
確認申請 用途:「倉庫業を営まない倉庫」
構造・設備の基準 建築基準法で定める基準
建築可能な用途地域 比較的広い用途地域で可能
「倉庫業を営む倉庫」
主な用途 他人から寄託された物品を有料で保管
関連法規 建築基準法、消防法、倉庫業法
確認申請 用途:「倉庫業を営む倉庫」
構造・設備の基準 建築基準法に加え、倉庫業法が定める厳しい施設設備基準
(強度、耐火、防水性能等)を満たす必要がある
建築可能な用途地域 住居系地域など、一部の用途地域では建築が制限される
1. 根拠となる法律の違い
一番の根本的な違いは、準拠すべき法律です。
・倉庫(自家用倉庫): 主に建築基準法と消防法の規制を受けます。
自社の製品や私物などを保管するためのもので、公共性や第三者への責任が比較的低いため、基準は限定的です。
・倉庫業を営む倉庫: 建築基準法と消防法に加えて、倉庫業法という法律の規制を強く受けます。
不特定多数の荷主から大切な財産を預かるため、その安全性を確保する目的で、より厳しい基準が設けられています。建築基準法上の扱いも、この倉庫業法の内容が前提となります。
2. 建築基準法上の具体的な違い
建築基準法の手続きや基準においても、以下のような具体的な違いが生じます。
建築確認申請上の用途:
自家用倉庫の場合、建築確認申請の際の用途は「倉庫業を営まない倉庫」(用途コード:08520)として扱われます。
一方で、倉庫業を営む場合は「倉庫業を営む倉庫」(用途コード:08510)として申請する必要があり、審査の内容もこれに基づき行われます。
3. 構造耐力や安全性に関する要求:
倉庫業を営む倉庫は、倉庫業法で定められる以下のような施設設備基準を満たす必要があります。
これが建築基準法上の審査でも考慮されます。
床の強度: 1平方メートルあたり3,900N(ニュートン)以上の荷重に耐えること。
壁の強度: 1平方メートルあたり2,500N以上の荷重に耐えること。
耐火・防火性能: 厳しい耐火性能や防火区画の設置が求められます。
防水・防湿性能: 雨水の侵入を防ぎ、湿気を防ぐための措置が必要です。
防犯措置: 施錠設備や照明など、盗難を防ぐための設備が求められます。
これらの基準は、一般的な自家用倉庫に求められる建築基準法上の基準よりも格段に厳しくなっています。
そのため、一般的な倉庫として建てられた建物を、後から倉庫業を営むために転用することは、大規模な改修が必要になる場合が多く、容易ではありません。
3. 用途地域による建築制限
建築できる場所(用途地域)にも違いがあります。倉庫業を営む倉庫は、不特定多数のトラックの出入りが想定されるなど、周辺環境への影響が大きいため、第一種・第二種住居地域など、住環境を保護するための地域では原則として建築できません。自家用倉庫も規模によっては制限がありますが、「倉庫業を営む倉庫」の方がより厳しい制限を受けます。
4. まとめ
建築基準法における「倉庫」と「倉庫業を営む倉庫」の最も本質的な違いは、**「他人の物を預かる事業かどうか」という点に尽きます。その事業性ゆえに、倉庫業法という特別な法律が適用され、利用者の財産を保護するためのより高度な安全基準(強度、耐火、防水など)**が建築物に求められます。この点が、建築計画や法的手続きにおいて最も重要なポイントとなります。
企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。
耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、
特殊建築物定期報告書検査作成
山梨県甲府市
吉野聡建築設計室
山梨県 甲府市 徳行3-3-25
TEL 055-222-6644
FAX 055-222-6100
mail yao@ruby.plala.or.jp
HP http://sekkei-y.com
facebook https://www.facebook.com/yaosekkei/
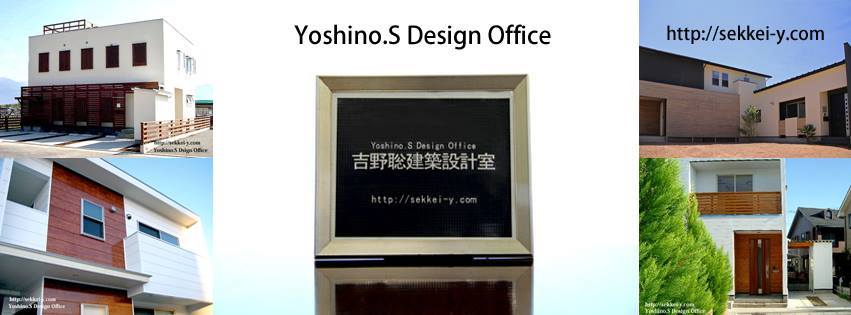
溶射屋
吉野さん
単なる倉庫とお金を得る倉庫ということでは当然違うのでしょうね。
加藤忠宏
倉庫業法初めて知りました
保険屋あい
こんにちは。
倉庫業を営むには、かなりの資金が必要ですね。
ハードルが高い業種ですね。