温暖化の影響でしょうか??
敷地や建物調査時に確認する・服につく雑草(くっつき虫、ひっつきむ虫)の種類が変わってきています。
建築物を建てる・今ある建物が建っている敷地(土地)の敷地調査。
新築・増築・改築・改修・リフォーム等の設計を行う上で、全てのスタートとなります
調査内容は、各関係法の行政機関との事前相談にはじまり、敷地や周辺の現状や環境の確認・敷地測量・地盤内の確認の地耐力調査もあります。
無数にある調査で、特に注意することが「道路境界線や隣地境界線」です。
お互いの権利が関係するので、時には双方の確認をして頂く事もあります。
その境界線は、整備されたところばかりではありません。
草むらの中での調査もあります。
そんな時にです!!
今年も多くの現場・敷地調査で、アレチヌスビトハギの襲撃にあってます。
アレチヌスビトハギは、ヌスビトハギによく似て北アメリカ原産の外来植物です。

ヌスビトハギ マメ科ヌスビトハギ属の多年草。ひっつき虫のひとつ。

北アメリカ原産の外来植物アレチヌスビトハギ
この植物は繁殖力が強く、日本の在来生態系に影響を与える恐れがあるため、「生態系被害防止外来種リスト」にも指定されています。
在来種のヌスビトハギと異なり、アレチヌスビトハギは日当たりの良い荒れ地に生育する傾向があります。
また、北アメリカ東部原産の多年生の帰化植物ですが、地域によっては冬に枯死するため、1年草とされる場合もあります。岡山県高梁市出身の植物研究家、吉野善介氏により1940年に大阪で採集されたのが国内における初めての記録とされます(清水建美編.2003.日本の帰化植物.平凡社.p.107)。日当たりが良く乾燥した環境を好み、北海道から沖縄まで全国に帰化していますが、特に西日本に多く、市街地の植え込みや空き地、道端などから、河川敷、田畑の畔、林縁など、攪乱がある環境に生育し、ときに群生します。少雨乾燥の岡山県南部では、ごく普通に見られる植物です。
果実の表面にはカギ状の細毛が密生しており、くびれた節の部分で容易に折れて、動物の毛や人間の衣服に付着して運ばれる(付着散布)、いわゆる「ひっつきむし」です。(重井薬用植物園より)
同じ苗字の岡山県の植物研究家、吉野善介氏により、
アレチヌスビトハギの和名「荒れ地盗人萩」は、1940年に本種を大阪府で採集し命名されたとの事です。
企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。
耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、
特殊建築物定期報告書検査作成
山梨県甲府市
吉野聡建築設計室
山梨県 甲府市 徳行3-3-25
TEL 055-222-6644
FAX 055-222-6100
mail yao@ruby.plala.or.jp
Web https://sekkei-y.com
facebook https://www.facebook.com/yaosekkei
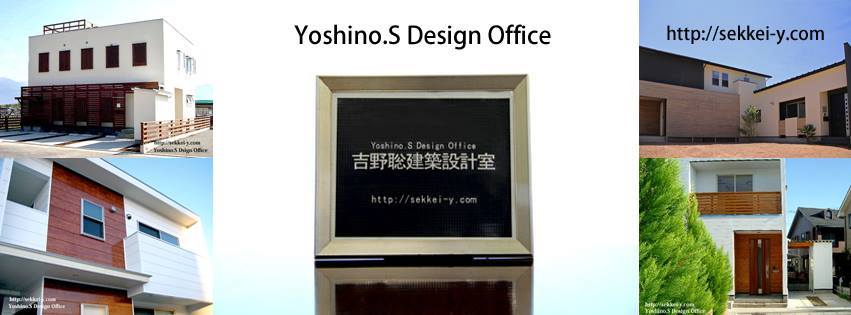
加藤忠宏
俗称盗人ハギですね。