軸組工法(在来工法)は、日本の木造住宅で古くから用いられてきた伝統的な建築方法です。
主に柱、梁、土台、筋かいといった部材を組み合わせて建物の骨格を作ります。
かつては「継手(つぎて)」や「仕口(しぐち)」と呼ばれる、木材自体を加工して組み合わせる方法が主流でしたが、1995年の阪神・淡路大震災をきっかけに建築基準法が改正され、現在は建物の耐震性を高めるために接合金物を使用することが一般的になっています。
これらの金物は、地震や台風といった大きな力が加わった際に、木材の接合部が抜けたり、壊れたりするのを防ぐ非常に重要な役割を担っています。
主要な接合金物の種類と役割
建物の各部位で、力の加わり方に応じて様々な種類の金物が使われます。
・基礎と土台、柱をつなぐ金物
地震の揺れで建物が基礎からずれたり、柱が土台から引き抜かれたりするのを防ぎます。
・アンカーボルト
建物の土台とコンクリート基礎を連結するためのボルトです。建物全体が基礎から動かないように固定する、最も基本的な金物です。
・ホールダウン金物(引寄せ金物)
地震時に柱が土台や梁から引き抜かれる力(引抜き力)に抵抗するための、非常に重要な金物です。建物の角や筋かいの入った耐力壁の柱など、特に大きな力がかかる部分に取り付けられます。基礎から柱まで伸びる長いボルトで強力に固定します。

柱・梁・筋かいをつなぐ金物
建物の骨格を強固に一体化させ、地震の横揺れなどに対抗します。
・羽子板ボルト
梁が柱や別の梁から抜けてしまわないように固定する金物です。ボルトの端が羽子板のような形状をしています。主に梁と梁、梁と柱が交差する部分で使用されます。
・筋かいプレート
建物の耐震性を高める部材である「筋かい」の端部を、柱や土台・梁にしっかりと固定するための金物です。地震の横揺れで筋かいが外れるのを防ぎます。
・短冊金物
柱と梁、または梁同士を平面的につなぎ合わせる短冊状の金物です。木材の接合部を補強する役割があります。
・水平構面(床・屋根)を固める金物
床や屋根の水平方向の剛性を高め、建物のねじれを防ぎます。
・火打ち金物(火打ち梁・火打ち土台用)
床や小屋組の角の部分に、水平方向の変形を防ぐために斜めに取り付けられる「火打ち」という部材を固定するための金物です。
・くら金物(鞍金物)
小屋組などで、母屋(もや)や棟木(むなぎ)といった部材が小屋束(こやづか)から離れないように上から被せて固定する金物です。
これらの接合金物は、建物の安全性と耐久性を確保するために不可欠な部材です。建築基準法にもとづき、建物の構造計算(N値計算や許容応力度計算)によって、どの場所にどのくらいの強度の金物が必要かが厳密に定められています。
企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。
耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、
特殊建築物定期報告書検査作成
山梨県甲府市
吉野聡建築設計室
山梨県 甲府市 徳行3-3-25
TEL 055-222-6644
FAX 055-222-6100
mail yao@ruby.plala.or.jp
Web https://sekkei-y.com
facebook https://www.facebook.com/yaosekkei
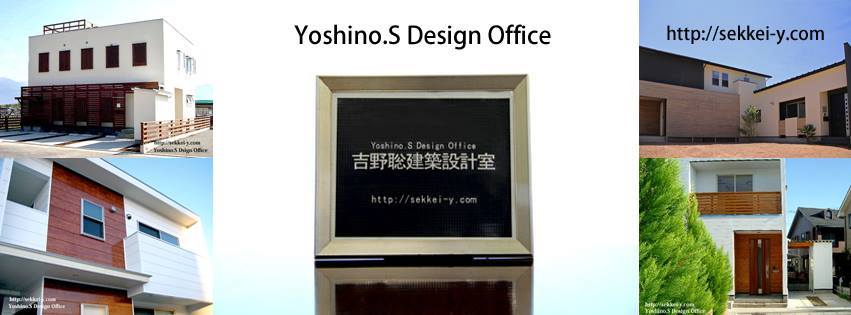
溶射屋
吉野さん
建築中の接合金物みるの好きです(^^;
どんな形をして、どのような効果があるのかと気になってしまいます。
加藤忠宏
静岡は地震が怖いので